|
角川書店 エーデルワイスシリーズ全6巻
|
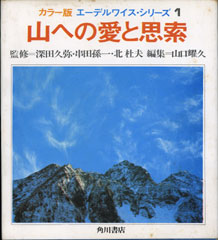
山口耀久「北八ッ彷徨」の名前はかなり前、山の本を始めて読んだ頃から知っていた(それはなんでかという話は別途・・・)、と前回書いたがその続きが今回である。
「カラー版エーデルワイス・シリーズ」全6巻は昭和43年、角川書店から刊行された。監修が深田久弥、串田孫一、北杜夫で当時の有名な山の文学を集めたもので、中には多数のカラーグラビアもある。一冊490円。
ぼくがこの本の一部の巻を読んだのは、高校の図書館で第5巻が最初だったと思う。
各巻の目次をこちらにスキャンしたが、第5巻の収録作のひとつに「北八ッ彷徨」に収録される「雨池」がある。まだ世間にはよく知られていない頃の雨池でキャンプをして、いかだで遊ぶこの一文はぼくの中での北八ヶ岳のイメージ作りに大きく貢献した。
また同じ巻には田部重治の「笛吹川を溯る」も収録されていた。笛吹川東沢を遡行したこの記録は田部の文章の中でも「数馬の一夜」とともに大変有名なものであることを後に知るが、山歩きを始めて間もない学生にとってこの一文は奥秩父への強い憧れを植えつけるには十分すぎるものであった。
田部の文章を読んだのは間違いなくこの本が最初で、これを読んだあとに、二見書房から山岳名著シリーズの1冊として田部の「わが山旅五十年」が刊行されるのを雑誌山と渓谷で知ると、すぐに購入してむさぼるように読んだ(残念ながら二見書房の本は実家にて廃棄され、手元にあるのは平凡社ライブラリーの一冊である)。
このシリーズの良さはふたつある。

ひとつは山の名著やすばらしい写真を手軽に楽しめる点である。まあ、それを狙ったものだから当然といえばそうなのであるが、単行本にはなかなか手がでなくてもこういうオムニバスの中で気に入ったものが見つかれば、先に記載したぼくのようにその後でちゃんとはまる道が開ける。
特に多数のカラー・モノクロのグラビア写真は、その巻にあったイメージのものが多く、三宅修など当代の有名写真家になるものであったため、それ自体だけでもすばらしい。
特に左の写真は当時持っていたたぶん日地出版のガイド地図「霧ヶ峰」にも使われていて、霧ヶ峰のイメージをいやおうにも高めてくれた。
もうひとつは、山の本に興味がある人でも、通常ではなかなか手にしない、たとえば当時の大学受験生を大いに悩ませた評論家・小林秀雄や亀井勝一郎の山のエッセイなども読めてしまうことだ。
小林秀雄が深田久弥と親交があり山に行くことは深田の文章に何箇所か登場するので有名ではあるが、亀井勝一郎のような大和・飛鳥・聖徳太子というイメージの人に八ヶ岳登山の一文があることはなかなかわからない。
このシリーズがぼくに及ぼした影響はかなり大きいのは事実ではあるが、出会った当時は半分くらいしか読まなかった(と思う。今、目次を見ても思い出せない巻がある・・・)。
こういうオムニバスの全集ものは図書館で借りるのも良いが、手元にあってこそ価値がある。一文が長くないのでときどきパラパラとめくり一節を読んだり写真を眺めたりしたい、ということで極めて限られたぼくの本箱に納まる要件を満たしている。
神田の古本屋でバラのものを時々見かけることはあったが特にほしいというほどのこともなくすごしていたが、先日、悠久堂でたまたまこの第5巻を手に取り、目次を見たら、上に書いたような事実がいっぺんに甦ってきた。その日は次の予定もあり購入しなかったが、ネットで検索すると値段はばらばらながら全巻セットでもあまり高くない。ぼくは6巻を3,000円+送料300円で購入した。大体2千円から6千円くらいで、中には1万円以上の値段をつけている店もあるようだ。悠久堂の6巻セット価格は失念したが第5巻は500円だった。その近隣店では9千円。
ちなみに一挙に6巻も蔵書が増えたのでスペース捻出のため、山に関係ない本83冊がブックオフの在庫になった。
|
|
|
|